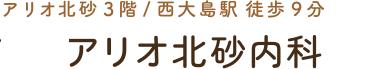睡眠時無呼吸症候群とは
寝ている間に呼吸が止まったり、呼吸の回数が減ったりするのを繰り返す状態を睡眠時無呼吸症候群と言います。睡眠時の無呼吸や低呼吸を繰り返すことで血中酸素濃度が下がり、全身や脳に酸素不足が生じます。
それだけではなく、心臓や血管にも負荷がかかります。また、睡眠の質が下がることで、昼間に強い眠気に襲われることがあります。睡眠時無呼吸症候群が原因による大きな事故を引き起こすこともあるため深刻な問題となっています。国内には、睡眠時無呼吸症候群罹患者がおよそ200万人いるとも言われています。
しかし、ご自身で気付くことが難しいことがあるため気付かずに過ごしている人も多くいます。睡眠時無呼吸症候群は、心疾患や脳血管疾患を発症するリスクが高いため、軽視できません。
睡眠時無呼吸症候群の合併症
心臓病
睡眠時無呼吸症候群の方は、発症後心血管狭窄や閉塞など心臓病を発症するリスクが高いと報告があります。
脳血管障害
睡眠時無呼吸症候群の症状が重度の場合、脳梗塞や脳卒中の発症リスクが高くなります。
糖尿病
睡眠時無呼吸症候群の無呼吸症状が重度になるにつれて、糖尿病を合併しやすいと報告されています。
高血圧
睡眠時無呼吸症候群の方は高血圧を合併していることが非常に高いことが分かっています。
睡眠時無呼吸症候群の種類
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)と、中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)に分類されます。一般的に罹患者数が多いのは、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)です。
睡眠時無呼吸症候群の症状
睡眠中の無呼吸や低呼吸が主な症状です。ただし、寝ている間の症状のためご自身で気付くことは難しいとされています。自覚できる症状としては、日中に襲う強い眠気、起床時の倦怠感や疲労感、集中力低下、頭痛、抑うつ症状、夜間の頻尿、胃腸症状、口呼吸における喉の炎症などが挙げられます。
寝ている間は、大きないびき、苦しそうないびきなどが特徴として起こるため、家族など側にいる人に指摘されて気付くこともあります。
睡眠時無呼吸症候群の検査
エプワース眠気尺度(ESSEpworthSleepinessScale)、ご自宅での簡易検査、入院が必要な終夜睡眠ポリグラフ検査などがあります。
エプワース眠気尺度(ESSEpworthSleepinessScale)
主観的な眠気を判断するチェック表です。ご自身で該当するものをチェックして、その合計点で判断していきます。 16点以上で重症、11点以上で睡眠時無呼吸症候群の可能性ありとされます。
簡易検査
医療機関から検査装置を貸しだして、ご自宅で検査が可能です。寝る際に顔と手にセンサーを着けて睡眠中の呼吸や酸素濃度を調べます。検査データを医療機関に戻して分析、診断を行います。
終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)
入院しながら検査を行います。睡眠時の呼吸や酸素濃度のほか、眼球運動や脳波、体温、心電図、炭酸ガス濃度、いびきなどを測ります。
睡眠時無呼吸症候群の治療
CPAP療法
ご自宅で出来る専用装置を使用した、持続陽圧呼吸療法です。睡眠中に専用のマスクを装着して気道を確保し、気道の狭窄や閉塞を防ぎます。気道が確保されることで無呼吸や低呼吸を予防していきます。睡眠中の無呼吸や低呼吸を減らすことで、昼間の強い眠気の解消に繋げます。一般的に多い閉塞性睡眠時無呼吸症候群の主な治療法として、CPAP療法を行います。
保険診療の主な流れは、以下の通りです。
問診
自覚できる症状や気になることについてお伺いします。
簡易検査
専用の検査機器をお貸しし、ご自宅で検査をしていただきます。睡眠時の呼吸の状態や酸素濃度を調べます。
再受診
ご自宅での検査後、検査機器をご返却ください。1時間あたりの無呼吸数と低呼吸数の平均AHI(無呼吸低呼吸指数)を参考に診断します。
| AHI数値 | |
|---|---|
| 20以下 | CPAP療法でない治療方法を検討します |
| 21~39 | 入院しながらポリグラフ検査を行い、検査結果からCPAP療法の必要性を検討します |
| 40以上 | CPAP療法が必要です |
CPAP療法以外の治療方法
生活習慣の改善
閉塞性睡眠時無呼吸を引き起こす要因として、肥満が挙げられます。このため、適度な運動や食事習慣の改善を行い、減量を図ります。また、アルコール摂取によって筋肉が弛緩されると無呼吸や低呼吸になりやすいため、飲酒をしていただきます。また、寝る際の姿勢では、仰向けになると気道が閉塞しやすいため横を向いて寝るなども提案しております。
外科的治療
外科的治療は稀なケースですが、口蓋垂軟口蓋咽頭形成術を実施することがあります。
マウスピース装着
寝る際に専用のマウスピースを装着し、気道を確保します。この場合は、歯科受診をしてオーダーメイドで作成します。
お気軽にご相談ください
睡眠時無呼吸症候群を発症し、治療が必要な状態にも関わらず受診していない方は約85%以上もいると言われています。日中の強い眠気や集中力の低下は、大きな事故を引き起こす恐れがあります。睡眠中の大きないびきなど、ご家族などに指摘された場合や、日中の疲労感、強い眠気など気になる症状がある場合には、早めに当院までご相談ください。